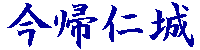
----�@�Ȃ��������@----
�ʖ��F�k�R�� �ق�������
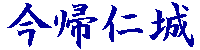
----�@�Ȃ��������@----
�ʖ��F�k�R�� �ق�������
����24�N1��4���쐬
����24�N1��4���X�V
�k�R������іk�R�Ď�̋���

���A�m���s����u�c�^��s�������낷
�E�f�[�^
�E���A�m��T�v
�E���A�m��ւf�n�I�i�o��L�j
�E���A�m����
�@
| ���� | ���A�m�� |
�Ȃ������� |
| �ʖ� | �k�R�� |
�ق������� |
| �z�� | 13���I�����납��z�邳�ꂽ�炵���i���A�m������ψ��� �u�Ȃ�����3�v�j�B |
|
| �j�p | 1665�N�k�R�Ď炪�Ɉ����グ�p��ƂȂ����i�V�l�������� ���{��s�̌n1 �w���A�m�O�X�N�x�j�B | |
| ���� | �R�� | |
| ���� | �ΐς� | |
| �ꏊ | ���ꌧ�����S���A�m���������i���������j | |
| �A�N�Z�X | ���A�m��́A��܂��Ɍ����Ɠߔe��`���獂���ɏ���Ėk����ڎw���A�k���܂ōs���ΕW�����o�Ă���̂ʼn��Ƃ��Ȃ�B �Ƃ������ƂŁA�ߔe��`���X�^�[�g���A����332�������E�܂��ēߔe�s�X���ʂ�ڎw���B��3Km��ō���332�����͍���331�����ɕς�邪�A�����Œ��i����u����E�ߔe�s���v�A�E��O�ɃJ�[�u����u�����E�L����v�֍s���킯�����A�����͂܂��������B�����500����́u�R���v�����_�ʼnE�܂��悤�B�܂������ł��s����͂��Ȃ̂����A�^�N�V�[�ɏ��ƂȂ����E��I������̂ŁA�Ђ���Ƃ���Ƃ܂������͏a�������̂��낤���B ���ĉE�܂��A��600����́u�R���i��j�v�����_�̓��m���[���̍��˂�����̂ŕ�����₷���B���������܂��A���m���[���̉��𑖂낤�B���̂܂ܓߔe�勴��n��A200���قǍs���ƉE�Ԑ��͍��˂ɂȂ��Ă��܂��̂ō��Ԑ��̉��̓����s�����B100�����炢�Łu�Ôg���v�����_�Ȃ̂ʼnE�܂��B�����Ɓu���ꎩ���ԓ��@�P�ߔe���v�̗̕W�����o�Ă���̂ŊԈ��Ȃ����낤�B�����������́u�ߔe�v�C���^�[�ł͂Ȃ��A�u�앗���k�v�C���^�[���獂���ɓ��邱�Ƃɂ��悤�B���炭�܂������s���A��6Km��́u�^�ߔe�v�����_�ō��܂���B�u�앗���k�@������ʁv��ڎw���̂��B���̂܂܉E�Ԑ����ێ����A�ߔe��`���H�u�앗�������ԓ��v�ɓ��낤�B �����A��������͉��ꎩ���ԓ����Ђ����瑖��A��60Km��̏I�_�܂ʼn��K�ȃh���C�u���B�ԈႤ�Ƃ���A�I�_��O�̋��c�i���傾�j�ňɕ����E���c���ʂ֍~��Ă��܂����Ƃ��炢���Ǝv���B�������~�肸�ɖ���E�{���̏I�_�܂ōs���̂��B�I�_�܂ōs���ƁA�������H�͎��R�ƍ���58�����ɍ�������B�������獡�A�m��܂ŁA����25Km���炢���B ���āA����58�����ɍ������A��5�D5Km��́u��P���ځv�����_�ʼnE�܂��B���Ƃ��C�ɂȂ�����_�������A����͋߂��ɖ���邪���邩�炾�낤�B�ڈ�͖���s������500����O���B �E�܂��Ė�3Km�i�ނƁA�u�ɍ���v�����_�Ȃ̂ł��������܁A�u����v��ڎw���̂��B��������3Km�s���ƍ���505�����ɓ˂�������B�u����v�����_���B���������܂��悤�B��������͂Ђ�����܂������s�����B��8Km��̍��A�m�������ڎw���Ɨǂ��B�r���A�x���H�����邪�E�֍s���ƌ���72�����Ȃ̂ŁA�����͍��i�ݍ���505�������L�[�v���B���A�m������̑O�ɂ́A�u�����A�m��v�̕W���������Ĉ��S�ł��邼�B�����5Km�s���ƁA����Ɂu�����A�m��ՁA���A�m�����j�����Z���^�[�v�̕W�����o�Ă���̂ō��܂��悤�B�����ɂ͌����_�����Ȃ����M�����Ȃ��B�W�����������肾���A�傫�ȕW���Ȃ̂Ō����Ƃ����Ƃ͂Ȃ����낤�B���܂���ƁA�u���A�m��ՂPKm�v�̕W��������̂Ŋm�F���悤�B�⓹������čs���Ɩ�1Km��ɁA�u���A�m��Ձv�̕W��������ɏo�Ă���A�E��ɍ��A�m�����j�����Z���^�[������̂ŁA�����ɒ��Ԃ���̂��B �����ւ�ꂳ�܂ł����B�����s�����������A����{���̑傫���������ł���h���C�u���Ǝv�����B�����Z���^�[�Ɍ�����������̂œ��ꌔ���A�����A����T�K���I |
|
���u��v�̌Ăѕ��ɂ���
����ł́A��Ə����ăO�X�N�ƌĂԁB
�܂�A��i�O�X�N�j�Ƃ����̂́A����n���̂���̌ď̂��B���̂���͖{�y�̂���Ƃ͐����ƈ���Ă��āA�Ȃ��肭�˂����Ί_����ۓI���B
�ƂȂ�ƁA����̂���͂ǂ��Ăׂ����̂��낤���H
�Ⴆ�A�n���Ƃ��Ă̖L����͌��n�ł̓g�~�O�X�N�Ɠǂނ��A�ł͖L����ɂ��邨��́A
�@�@�@�L���� �Ə����āA�g�~�O�X�N�ƌĂ�
�@�@�A�L����� �Ə����āA�g�~�O�X�N�W���E�ƌĂ�
�@�@�B�L����� �Ə����āA�g�~�O�X�N�O�X�N�ƌĂ�
�̂ǂꂪ�ӂ��킵���̂��낤���B
�K�C�h�u�b�N�Ȃǂ͌��\�A�A�̂悤�Ɂu�����O�X�N�W���E�v�Ɓu��v�̎����d�˂ď����Ă���̂������B�������ɍŌ�Ɂu�W���E�v�����Ɠ���݂₷���A�Ƃ�����������Ղ��B
�Ȃ��ɂ͇B�̂悤�ɁA�u�����O�X�N�O�X�N�v�ƒ��J�ɏ����Ă�����̂����邪�A����͍s���߂����낤�B
�������A�����̉���A�܂藮���̐l�����́A�����W���E�A�Ƃ͌ĂȂ��������낤�B���������A�����W���E�ƌ����Ή���ł́�����̂��Ƃ��B�����ŁA���̃z�[���y�[�W�ł́u��v�̎����d�˂��A�����O�X�N�ƌĂԂ��Ƃɂ��悤�B
�Ƃ����Ă��A���܂肱����邱�ƂȂ��A�Ⴆ�����͒ʗ�ɂ��������u�V�����W���E�v�ƌĂڂ��B
�����A�m��T�v
���A�m�i�Ȃ�����j�O�X�N�͉���k���̒��S�������邾�B�z��́A�o�y�╨����P�R���I�㔼�Ƃ���邪�A�z��҂͕�����Ȃ��i���A�m������ψ��� �u�Ȃ�����3�v�j�B�@�Ƃ��������A���̍��̉���̗��j���̂��悭�������Ă��Ȃ��B
���A�m��͋K�͂��傫���A���̍�Ɨʂ��l����Ƒ����̌��͂̏W�����������͂��ł���A�R���e�n�̈i�i�����j�͖k�R�i���A�m�j�ɏW��Ă����Ƃ������������i���A�m������ψ��� �u�Ȃ�����3�v�j�B�K�͂��傫���Ƃ����Ă��A��������悤�ȑ傫�ȐΊ_���͂��߂��炠������ł͂Ȃ��͂����B�u�i�i�����j�v�Ƃ����̂́u���̎��i��̂ʂ��j�v�Ƃ��Ă��n���̗L�͎҂Ȃ����x�z�҂̂��Ƃ��B�{�y�ł������l�̎�Ƃ������Ƃ��낾�낤���B
�Ȃ��A�`���ł́A���A�m��̓A�}�~�L���_�̌���ł���u�V�����i�Ăj�v���������A�Ɖ]���Ă��邻�������A����́A�z��҂̕�����Ȃ��e�n�̌Â��O�X�N�͂قƂ�ǂ��u�V�����v�̒z��Ƃ������ƂɂȂ��Ă���炵���B�����ЂƂA����ɂ͌��ג��i�݂Ȃ��Ƃ̂��߂Ƃ��j�㗤�`��������A�ג������n�ł��������q����w�i���������j�Ɩ��t�����A�̂��ɍ��A�m���ɂȂ����A�Ƃ����`�������邻�����i�^���x���� �u�V���������j2�v�j�B
���āA���A�m�ɂ��Ă͂�����Ƃ��Ă���̂́A�����́u�����^�v�ɖk�R���i�ق������j�̜�����i�͂ɂ��j�E�a�i�݂�j�E�����m�i�͂j�R�l�̉����L�^����邱�낾�B�N��Ƃ��ẮA����ł��͂��߂Ė����ɐi�v�����̂����̍^���P�U�N�i1383�j�ł����i�^���x���� �u�V���������j2�v�j�̂ŁA�{�y�ł͓�k������̂���肾�B��q�̂悤�ɁA���A�m�邩��͂P�R���I�㔼�̈╨���o�y���Ă���̂ŁA����ł����ȑO�ɒ����ƌ��Ղ��Ă����̂͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv���邪�A���̖����`����Ă��Ȃ��̂��B
���̍��̉���́A��R�i�Ȃ�j�E���R�i���イ����j�E�k�R�i�ق�����j�̂R���͂ɕ�����A�����Ă���A�u�O�R�����i�������j�v���邢�́u�O�R��������v�Ƃ����B�R�l�̈i�i���̎�j�́A���ꂼ�ꖾ�֒��v�����̍����i�����ق��A�����ۂ��j���A�܂�R�̓Ɨ����������Ƃ��ĔF�߂��A���ꂼ��u���v�𖼏�����B���̂����k�R���̋��邪���A�m�邾�B
�O�R�̉��́A���ꂼ�ꖾ���ɐi�v�����킯�ł��邪�A���͓̉�R�Q�X��A���R�T�O��ȏ�Ɣ�זk�R�͂P�W��Ƃ��Ȃ菭�Ȃ��A����͖k�R�������Ƃ��_�Ɛ��Y�����Ⴂ���߂ł��낤�ƍl�����Ă����i���A�m������ψ��� �u�Ȃ�����3�v�j�B�Ȃ��A�O�R���疾�ւ̍v�����͎�ɔn�Ɨ����ł������i�^���x���� �u�V���������j2�v�j�B�@�����̂ق��́A���V���̐��ɂ��̖����Y�o�����������i�������Ƃ肶�܁�������蓇�j������̂łƂ������A�n�Ƃ����͍̂�����l����ƕs�v�c�ȋC������B
���̍^���P�U�N�i1383�j�A���R���E�@�x�i�����Ɓj�͖��c�邩�瑮���̉��Ɏ�������t������i�Ƃ���j�����B���̂Ƃ��̎@�x�i�����Ɓj���ɑ���قɁA�u��������A���Ă����g�҂������ɂ́A�����̎O���݂͌��ɑ����A�_��p�����������Ă���Ƃ����B���͂͂Ȃ͂������i���ꂤ�j���̂ł���B���͐킢����߂�悤�Ɂv�Ƃ������B�̂��A���c��͓�R���Ɩk�R���ɂ��ق��A�u���͎O�����������Ă��邱�Ƃ�J���Ă���B�i��R�E�k�R�́j�͂����m��B�A�悭�����ӂ�̂��āA�������~�߂�v�Ƌ��������Őӂ߂Ă���B�����ŎO���͑������~�߁A�g�҂��c��ɔh�����āA�c��̐S�����Ɋ��ӂ̈ӂ�\���Ă��邪�A�k�R���E������i�͂ɂ��j�͂��̂Ƃ��ɏ��߂Đi�v����̂ł����i�^���x���� �u�V���������j2�v�j�B�@�k�R�E������i�͂ɂ��j�̎g�҂͖͌��K�ŁA�����ɕ����サ�����Ԃ�ɕz��P���������Ƃ����i�V�l�������� ���{��s�̌n1�w���A�m�O�X�N�x�j�B
���̂Q�N��^���P�W�N�i1385�j�A�����c��͜�����i�͂ɂ��j�ɑ��t������i�Ƃ���j���������B������i�͂ɂ��j�������ɗ������R�k���ƂȂ�̂͂��̂Ƃ�����ł����i�^���x���� �u�V���������j2�v�j�B�Ȃ��A�����ł͖k�R�i�ق�����j�ƌĂԂ��A�����ł͎R�k�ƌĂ�ł��āA�������Ђ�����Ԃ�B
�^���P�U�N�i1383�j�ȗ��A������i�͂ɂ��j�͂U��A���̎q�E�a�i�݂�j�͂P��A�����m�i�͂j�͂P�P��A���ɐi�v���Ă����i���A�m������ψ��� �u�Ȃ�����3�v�j�B�@�a���̐i�v�����Ȃ��̂́A�݈ʖ�T�N�Ƃ����Z���������������߂��B�a���p�����̂́A���̎q�̝����m�ł����i�^���x���� �u�V���������j2�v�j�B
�Ƃ���ŁA�����k���āA�͂�����Ƃ��������͕s���ł�����̂́u�k�R�����v�Ƃ����`��������Ƃ����̂ŋL���Ă������B���A�m�̐��̎��i��̂ʂ����i�j�ɔN�V���Ă��琢�p�������܂�A��㏼�i����܂j�Ɩ��t����ꂽ�B�Ƃ��낪�A�d�b�̖{������i���ƂԂ��ӂʂ��j���d�����������A���̎�͎E���ꂽ�B���̎�̍ȂƑ����͐�㏼��A��ē��������A�Ȃ͗͐s���A���Ƃ𑤎��ɑ����Ďu�c�^���i�����܂���j�ɐg�𓊂����B�����͎u�c�^���o�g�̉��M�i���Ƃ���j�Ƃ����A��㏼����Ă��B�P�W�N��A��㏼�͐������u�t�i�����͂�j�Ɩ������߁A�̂����b���W�߂Ė{���������A�m���D�҂����A�Ƃ����`���ł���B���̌�A�ǂ̂��炢�̎��Ԃ��o������������Ȃ����A���A�m�i�͉H�n�i�͂˂��j�i�ɍU�ߖłڂ����B���̂Ƃ��̍��A�m�i���u�t���������ǂ����͕s�����B���̉H�n�i�́A����Ɍ����i���˂��j�Ƃ������邪�A�̂������ɐi�v����B�����ł́A���̔�������u������i�͂ɂ��j�v�ƕ\�����Ƃ����B�܂����k�R������ł��i�^���x���� �u�V���������j2�v�j�B
�k�R���E������i�͂ɂ��j�����̂͂͂����肵�Ȃ����A�^���Q�W�N�i1395�j�ɂ́u�R�k���a�i�݂�j�v���i�v���Ă���̂ŁA������O���ƍl�����Ă���B�a�i�݂�j�͜�����i�͂ɂ��j�̎q�ł���Ƃ����B�Ƃ��낪�A���̎��ւ͂���߂ď��Ȃ��A���̗��N�^���Q�X�N�i1396�j�ꌎ�ɂ́A�k�R���E�����m�i�͂j���i�v���Ă���A�a�i�݂�j�͊��ɖS���Ȃ��Ă���B�u���R�����v�ɂ����a�i�݂�j�݈̍ʂ͌ܔN�Ƃ����i�^���x���� �u�V���������j2�v�j�B
�a�i�݂�j�̐Ղ��p�����͎̂q�̝����m�i�͂j���B�u���R�����v�A�u���z�v�ɂ͝����m�i�͂j�́A�������畐�E�����݈̂��s�����Ȃ�A�Ƃ���A�Ƃ�ł��Ȃ��l���������悤���B�����Ƃ�����́A�k�R������łڂ������̋L�q�Ȃ̂ŁA�����̂悤�ɑ������x���₵���B�Ƃ����Ă��A���ɐl�������M����悤�Ȃ��̂��Ȃ��̂ŁA���͂��̂Ƃ��肾�Ƃ��āA�b��i�߂悤�B�����m�i�͂j�̏��E�{�������i���ƂԂā[�͂�j���E�͂���߂ċ����A���m�����E�ł������B�����m�͒��R�i���イ����j���U�����悤�Ɠ��镺�n�̌P�������Ă����B�Ƃ��낪�A�����m�́u���s�����v�ł���̂ŁA�H�n�i�i�͂˂������j�E�����i�i���ɂ��݂����j�E����i�i�Ȃ������j�Ƃ������k�R�̈i�͒��R�֓��~�����B���̂���̒��R���͎v�Љ��i�����傤�����j�������B�v�Љ��́A�q�̏��b�u�i���傤�͂��j�ɖk�R�����𖽂����B�i�y�P�S�N�i1416�j���邢�͉i�y�Q�O�N�i1422�j�A���b�u�͉Y�Y�i�i���炻�������j�E�z���i�i�����������j�E�ǒJ�R�i�i��݂����j�̕����������č��A�m��֍U�ߊ��i�^���x���� �u�V���������j2�v�j�B
�U��R�́A����i���ē��Ƃ��ĉz���i�E�ǒJ�R�i��̑叫�Ƃ��Ĕ��S�]�l�A���ɂ͍����i�E�H�n�i��叫�Ƃ��ē�玵�S�]�l�ōU�߂�B�Ƃ��낪���A�m��͌�����ւ�A�O���ԍU�ߑ����Ă����ނ���Ă��܂����B�����ŏ��b�u�͌v����p���邱�ƂƂ��A���S�̖{�������i���ƂԂā[�͂�j�͗E�͂ɗD��Ă��邪���͂Ɏア�̂ŁA��A�ɂ܂���Ė��g�𑗂�A�d�G���Đ��������Ƃ���A�{�������i���ƂԂā[�͂�j�͂���ɉ������B�����A�{�������i���ƂԂā[�͂�j�͝����m�i�͂j�ɁA�u�v���������o�Đ���Ă��Ȃ��̂ŁA�G�͂����Ɖ�X�����a�҂Ǝv���Ă���͂����A���݂ɏ���o�Đ킦�ΓG�͕K��������v�Ɛi�������B�����m�i�͂j�́A���������A�܂���������J���ē����ďo���B���b�u�́A�������̂����Ƃ����j�ȕ��p�����ɐN��������ƂƂ��ɁA�{���͝����m�̍U�����Ĕs�������B�����������m���ӂƐU��Ԃ�Ə�͉ɕ�܂�Ă����̂ŁA�}����֖߂����Ƃ���{�������̗����m�����B���b�u�R�͏�ւȂ��ꍞ��ł��Ă���A�����m�i�͂j�͏钆�̗���A���Q�����i�V�l�������� ���{��s�̌n1�w���A�m�O�X�N�x�j�B
�������Ėk�R�����͖łт��킯�����A�Ō�̖k�R���E�����m�i�͂j�͍��E�ł͂��邪���̈����A���̂Ȃ��l���Ƃ������Ƃ��낾�B����D�ɗ����Ȃ��̂́A��O�֓����ďo�������m���G���������ꂽ�{�������̖d����m��A���͂₱��܂ŁA�Ɨ�����Ď��Q�����Ƃ������Ƃł��邪�A��Ƃ�������ɂ͍Ւd���J���Ă������̂ł��낤���A�Ւd�Ȃ����̂����Ƃ��d�v�ȏꏊ�ɂ������̂��낤����A����ȂƂ���܂ŏ�O����߂��ė���ꂽ�̂��낤���B�܂��`���ł��邩��A���܂�ׂ����F�����Ă��d���͂Ȃ����A�u���R���Ӂv�ɂ͂��Ⴄ�b�ɂȂ��Ă��āA���b�u�R����A�ɂ܂���ď�̂����Ƃ����j�Ȓf�R����ꕔ����E�э��܂��ď�ɉ��������Ƃ���͓��������A�����m�i�͂j���{�������i���ƂԂā[�͂�j���x����ď���o�Đ키�b�͂Ȃ��B�������̂ق����A���肻���ȋC�͂���B
�Ȃ��A���b�u�R�̖��g�Ȃ�ꏬ���������ɔE�э��ꏊ�́A���A�m��̂����Ƃ����j�ȏꏊ�Ƃ���Ă��邪�A�k�����Ƃ����쑤�Ƃ������Ă悭������Ȃ��B�����ƁA�u�c�^���i�����܂��傤�j�̂��Ƃł���A�ƒf���Ă���̂�����B�n�`���猩�āA��G�c�ɂ����Ă������̂ق��A�Ƃ����Ƃ��납�B
�Ƃ���ŁA���̏��b�u�̖k�R�����̎����ɂ��ẮA����͂Ȃ��B�u���R�����i���イ�����Ӂj�v�Ɓu���z�i���イ�悤�j�v�͎v�Љ��P�P�N�i�i�y�P�S�N��1416�j�A�u���R�����i���イ��������j�v�͏��b�u���ʌ��N�i�i�y�Q�O�N��1422�j�Ƃ��Ă����i�^���x���� �u�V���������j2�v�j�B�@
����ɂ��āA�u�Ȃ������R�v�ł́A1650�N�ɏ����ꂽ�u���R���Ӂv�́A�n���̎�����`�������Ƃɉi�\�Q�O�N�i1422�j�Ƃ����̂��낤�Ɛ������A����A�u���R���Ӂv�������u����{���R�����v�͉i�\�Q�O�N�i1422�j�����̂��Ă��邪�A����Ɏj������������1725�N�ɏd�C���ꂽ�u��{���R�����v���i�\�P�S�N�i1416�j�Ƃ��Ă���̂́A�����̎j���u�����^�v�ɋL����靳���m�i�͂j�̍Ō�̒��v���i�y�P�R�N�i1415�j�ł���Ƃ��납��A���̗��N�i�y�P�S�N�i1416�j�ɖŖS�������̂Ƃ݂Ȃ����̂ł��낤�Ƃ��A1743�N�́u���z�v��������p���ł���ƍl�@���Ă����i���A�m������ψ��� �u�Ȃ�����3�v�j�B
����́A�����̐����q��̘a�c�v�����̉i�y�Q�O�N�i1422�j����⋭������̂ŁA�����́A�k�R���E�����m�i�͂j�͉i�y�R�N�i1405�j����i�y�P�R�N�i1415�j�܂Ŗ�P�O�N�Ԑi�v���Ă��Ȃ��̂�����A�i�y�P�R�N�i1415�j�ȍ~���v�̋L�^���Ȃ�����Ƃ����Ă��̒���ɖk�R���łт��ƍl����K�v���͏��Ȃ��A�P�Ɏb���i�v���Ȃ���������L�^����Ȃ����������ł���A��������k�R�����i�y�Q�O�N�R���ɔj���Ă��̒n����������A�V�̒n���x�z����ړI�ŁA��������A�����N�̂����Ɏ��j�E�����i���傤���イ�j�����A�m��ɒ��݂����Ėk�R���Ď炳�����ƍl����ق����Ó��Ƃ��A�����i���傤���イ�j���i�y�Q�O�N�i1422�j�N�ɖk�R�Ď�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ���k�R�������m�ŖS�͉i�y�Q�O�N�i1422�j���Ó��Ƃ��Ă����i�V�l�������� ���{��s�̌n1�w���A�m�O�X�N�x�j�B
����ɑ��^���x�����́A�u���R���Ӂv�ɂ͂��������v�Љ��̋I���������ۂ�Ɣ����Ă���A���ʌp���͕��J���i�Ԃ˂��������@�x���̎q�j�����ꏮ���E���b�u���֔��ł��āA����͉i�y�P�X�N�i1421�j�ɏ��b�u�����J����łڂ����ƌ���Ă��邽�߂ł���Ǝw�E���i�^���x���� �u�V���������j2�v �w�k�R�x�j�A�������Ȃ��珮�b�u�����J����łڂ����͉̂i�y�S�N�i1406�j�ł���A�v�Ђ����J�̐��q�Ƃ��āu���v���J�̎����ɍ��������i�����ӂ��A�����ۂ��j�𐿂��A�������v�Ђ����������̂��i�y�T�N�i1407�j�A�����Ďv�Љ������̂��i�y�P�X�N�i1421�j�A�Ղ��p�����͎̂q�̏��b�u�ł��邪�����ł͉��ʂɓo�������̔N�����ʔN�Ȃ̂ʼni�y�Q�O�N�i1422�j�ɏ��b�u���ʁA���N�ɏ��b�u�͎��j�E�����i���傤���イ�j��k�R�Ď�ɔC�����A�m��֔h���A���ʂ��ĂR�N�ڂ̉i�y�Q�Q�N�i1424�j�ɖ����Ɏv�Љ����]�������āA���i�y�Q�R�N�i1425�j�ɍ����g��������K�ꐳ���ɗ��������R���ɕ�����ꂽ�i�^���x���� �u�V���������j3�v �w�v�Љ��E���b�u���x�j�A�Ɨ����������A�����Ȃ�Ɖi�y�Q�O�N�i1422�j�ɂ͂��łɎv�Љ��͖S���Ȃ��Ă���A�H�n�i�i�͂˂������j��̗v�����Ėk�R���E�����m�i�͂j�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ŁA�k�R�����͉i�y�P�S�N�i1416�j�����̂��Ă����i�^���x���� �u�V���������j2�v �w�k�R�x�j�B�@�Ȃ��A���b�u�������̎����R�N���o���Ă��疾���ɍ����Ă��闝�R�͂悭������Ȃ��B�����������邱�Ƃɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��悤�����A���J������v�Љ��ւ̐������f�����������ƂƖ��炩�ɈقȂ��Ă���B�v�Љ����ʂ��Ր��v���������̂ɔ�ׁA���b�u�͎��q�ł��邽�߂̗]�T��������Ȃ����A�����̉i�y�邪���̂Q�O�N�i1422�j�Ƀ����S���e�������̂Ō��茠�҂����Ȃ�����x�点���̂�������Ȃ��i�^���x���� �u�V���������j3�v �w�v�Љ��E���b�u���x�j�B�@���̉i�y��͖k�������������߃����S�������ւT����������i�{�e�~�q�� �u�����S���̗��j�v�j�A�i�y�Q�Q�N�i1424�j���̋A�r�ɖv�����i�^���x���� �u�V���������j3�v �w�v�Љ��E���b�u���x�j�B
�܂�Ƃ���A���R�̖k�R�����̔N�͌��ߎ肪�Ȃ��͂����肵�Ȃ��A�Ƃ����Ƃ���Ȃ̂ŁA���z�[���y�[�W�ł͗��_���Љ�邱�Ƃɗ��߂悤�B
�Ƃ���ŁA�k�R���E�����m�i�͂j���ł̂��̍��A�m��͂ǂ��Ȃ����̂��B��q�̂悤�ɁA�u�k�R�Ď�v�Ƃ����@�ւ�u�����̂ł���B���̖k�R�Ď�̋�̓I�Ȗ����A���x�ɂ��ẮA�u���R�����v�Ȃǂɉ����L����Ă��炸�A�͂����肵�Ȃ��B�ݒu�̖ړI�́A��ʂɁA�k�R�����牓���A�n�`���������A�����ɏZ�ސl��邌��ōĂє������N�������ꂪ���邽�߁A�Ƃ���Ă���B�i���A�m������ψ��� �u�Ȃ�����3�v�j�@����A�k�����ʌR�i�ߊ����邢�͖k�����E�Ƃ������Ƃ��낾�낤�B
��q�̂悤�ɁA�k�R���ŖS���i�y�Q�O�N�i1422�j�ł���A���b�u�͂��̒���Ɏ��j�E������k�R�Ď�Ƃ��Ĕh���������ƂɂȂ�B����́A�i�y�P�S�N�i1416�j�k�R�ŖS���ɂ��ƁA�����h���܂Ŗ�U�N���邪�A���̊Ԃɂ��ė^���x�����́A�썲���i�����܂�j�����̖����ɔC�����č��A�m��ɂ������Ƃ��A����͂��܂��܂ȓ`������M���邱�Ƃ��Ƃ��Ă���B�썲�ۂ́A�����m�U���̂Ƃ��̝���̑叫�A�ǒJ�R�i�i��݂����j�ł������B�����A�썲�ۂ��k�R�Ď�ƌĂꂽ���ǂ����͕�����Ȃ��A�Ƃ����i�^���x���� �u�V���������j2�v �w�k�R�x�j�B�@����Ƃ͕ʂɐܒ��Ă̂悤�Ȑ��ŁA�i�y�Q�O�N�i1422�j�k�R���E�����m�i�͂j��łڂ������b�u�́A�k�������̂��ߌ썲�ۂ����A�m��ɒu�������A���̔N�̂����ɑ��q������k�R�Ď�ɔC�����A�Ƃ����̂������i�V�l�������� ���{��s�̌n1�w���A�m�O�X�N�x�j�B
�썲���i�����܂�j�́A�����̓���̂悤�ȑ��݂ł��邪�A���̃G�s�\�[�h�͕ʓr�����i�Ȃ��������j�̍��ŏq�ׂ邱�Ƃɂ���B�����ɂ��ẮA���s�Ă��m�����{���Ă����̂ŕS���͐��Ƃ����n��͎��܂��Ă����Ƃ������i�V�l�������� ���{��s�̌n1�w�R�c�O�X�N�x�j�B���̖k�R�����̍��A�썲�ۂ͓ǒJ�R�i�ŁA�R�c���i��܂��������j������Ƃ��Ă����B�̂��ɂ͍��얡���i�����݂������j�A�����i�Ȃ��������j��z��A�C�z���Ă���z��̖��l�Ƃ���ꂽ�������B�܂��썲�ۂ́A������i�͂ɂ��j�i�ɖłڂ��ꂽ�u���A�m���̎�v�̌n���Ƃ����`��������B�Ƃ������Ƃ́A�u�c�^���M�i�����܂��Ƃ���j�ɕ�����č��A�m���E�o������i�E��㏼�̖���Ƃ������ƂɂȂ�̂�������Ȃ��B�����Ȃ�ƁA�썲�ۂ����b�u�ɏ]���k�R���E�����m�i�͂j�����͕̂��c�̂����������Ƃ������ƂɂȂ��i�^���x���� �u�V���������j2�v �w�k�R�x�j�B������i�͂ɂ��j�ɖłڂ��ꂽ�捡�A�m���̎��i�����Ȃ������̂ʂ��j����Ɉɔg�i�i���͂����j������A���̎��j���썲�ۂ̕��������Ƃ����i�^���x���� �u�V���������j3�v �w�v�Љ��E���b�u���x�j�B
���̐^�U�͕�����Ȃ����A�썲�ۂ��k�R�Ď�̒n�ʂɂ������Ƃ���A�i�y�P�S�N�i1416�j�k�R���ŖS����i�y�Q�O�N�i1422�j�̊Ԃ̖�U�N�Ԃ��A���邢�͉i�y�Q�O�N�i1422�j�k�R���ŖS�㐔�����ԂƂ������ƂɂȂ�B
�i�y�Q�O�N�i1422�j�����i���傤���イ�j���k�R�Ď�Ƃ��č��A�m��ɒ��C�����̂͊ԈႢ�Ȃ��悤���B���A�m���q�Ə̂����炵���i���A�m������ψ��� �u�Ȃ�����3�v�j�B�@�i�y�P�X�N�i1421�j�Z�\���Ŏv���i�����傤�j�������A�q�̏��b�u�i���傤�͂��j�����Ղ��p���B�����ł͂��̗��N�����ʌ��N�Ȃ̂ŁA�i�y�Q�O�N�i1422�j���b�u�����ʁA�����N�ɏ��b�u�͎��j�̏����i���傤���イ�j��k�R�Ď�Ƃ��č��A�m��ɒu�����B�썲�ۂ͋���̎R�c���i��܂��������j�ɖ߂����Ǝv���邪�A���̍��A���b�u��������Y�Y���i���炻���������j�������ֈڂ����悤���B�Ƃ������Ƃ́A�����̖k�R�Ď�h���́A�P�ɖk�������߂邽�߂Ƃ������́A���R�����̗����x�z�̋��_�Ĕz�u�̈�ƌ����������B�����A���̂Ƃ��ɂ͂܂���R���͌��݂ł���B�i�^���x���� �u�V���������j3�v �w�v�Љ��E���b�u���x�j�B
�R�c��ɖ߂����썲�ۂ́A�̂��V���ɍ��얡���i�����݂������j��z���Ĉڂ�B�铿�l�N�i1429�j���b�u�́A��R���E���D���i����܂��j��łڂ��ė����ꂵ���B���Ƃ��Ɨ����͑ΊO�f�Ղɒ��͂��Ă���A���b�u�̂���̓V�����A�p�����o���A�W�����Ƃ̌𗬂��s���Ă���B���{����́A���{�̉i���\��N�i1439�������̐����S�N�j���R�����`���i���������悵�̂�j����u�肤�������̂�̂ʂ��v�A���Ȃ킿���b�u�ɑ��Đi��i�̂���̏��Ȃ��͂����B�������A���̔N�̎l����\���A���b�u�͎����B�����`���̏��Ȃ��������ǂ����A������Ȃ��B�i�^���x���� �u�V���������j3�v �w�v�Љ��E���b�u���x�j
���b�u�̐Ղ��p�����̂́A���j�Ŗk�R�Ď�̏����i���傤���イ�j�ł���B�Ȃ����j���p���Ȃ��������͕s�����i�^���x���� �u�V���������j3�v �w�v�Љ��E���b�u���x�j�B
�ł́A���������Ƃ��ċ��������Ƃ̍��A�m��͂ǂ��Ȃ����̂��H�u���z�v�ɂ��A�����̎q���k�R�Ď�Ƃ��ĕ������߂��Ƃ����B�������A�N���k�R�Ď�ɂȂ������A�ǂ��ɂ��L�^����Ă��炸���O�͕�����Ȃ��B���܌���Y���́A�����̒�ł����u�����q�i������������j���k�R�Ď���p���A1469�N�̏������̕ς̂Ƃ����A�m�邩������g�����A�Ƃ����u��j�v���Љ�Ă����i���A�m������ψ��� �u�Ȃ�����3�v�j�@�B���̐^�U�̂قǂ͕�����Ȃ����A�������邢�͌썲�ۂɎn�܂����k�R�Ď�́A��ꏮ�����łт�܂ő����Ă����Ɛ�������Ă���悤���B
����͂������āA�����T�N�i1469�j�l����\����A�Q�X�̏������͓ˑR�����B�\�N�������Ƃ������邪�A���j�̏�őO�����̍Ō�̌N��͓��Ă��Ă���������̂ŁA�ǂ̒��x������������Ȃ��B�������̈�b�Ƃ��āA�C�O���Ղɗ͂����Ă����������́A���{�ւ��g�҂��������Z�N�i1466���������N�j�ɔh�����Ă���B�g�҂͋��֏��A������\�������R�����`���i���������悵�܂��j�ɉy�����āA�ޏo�̂Ƃ��ɖ�O�Łu�S�C�v��ł��炵�Đl�X�̓x�̂����Ƃ����B��C�̂��肾�����炵���i�^���x���� �u�V���������j4�v �w�������x�j�B�@���{�Ɂu�S�C���`���v�͓̂V���\��N�i1543�j�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��Ċw�Z�ł��ËL�������邪�A�������̂Ƃ��܂œ��{�ɓS�C���S���㗤�������Ƃ��Ȃ��A�Ȃǂƌł��l����K�v�͂Ȃ��A���̂悤�Ȏ����A���邢�͋L�^�Ɏc��Ȃ����Ԃ̌��ՂȂǂł��킶��Ɠ����Ă��Ă����ƍl���ĕs�v�c�ł͂Ȃ��B
���āA���������S���Ȃ�ƁA����ɂ͋v�����i���������܁j�Q�w�̊ԂɂƂ��������A���̏d�b�E�����i���Ȃ܂�j���N�[�f�^�[���N�����ĉ��ʂɏA���A���~�i���傤����j�Ɩ�������i�^���x���� �u�V���������j4�v �w�������x�j�B�@������̎n�܂�ł���B
���~���i���傤�����j�́A���b�u�i���傤�͂��j�̐��x�ɕ킢�A�k�R�ɊĎ��u�����Ƃ�����B�k�R�Ď�ɂ́A��b��֔ԂŔh�������Ƃ����i���A�m������ψ��� �u�Ȃ�����3�v�j�B�@���A�m�邪���������k�R�Ď�̋���Ƃ��Ďg��ꂽ�Ǝv����B
�����P�Q�N�i1476�j������\�����A���~�������B�݈ʂ͂V�N�ƒZ�������B�Ր��v���ɂ�葦�ʂ��ĂV�N�Ԃł́A��������̎����͏[���ȑ̐��Ƃ͌����Ȃ������̂ł͂Ȃ��낤���B���~�̐Ղ́A���j�̐^���˒M���i�܂��Ƃ��邪�ˁj���P�Q�ł��������߁A���~�̒�E������i���傤���j�����ʂ������̂́A�_�Ɋ������ꂽ�Ƃ������Ƃł����ɑވʁA���ǁA�^���˒M���i�܂��Ƃ��邪�ˁj�����ʂ����^�i���傤����j�Ɩ�������B���^���́A�ܕS�N�̗��������j�̂Ȃ��ōŒ��̂T�O�N�ԍ݈ʂ��A��������̊�b���ł߂邱�ƂɂȂ��i�^���x���� �u�V���������j5�v �w���~���E���^���x�j�B
���̏��^���̂Ƃ��A����܂ő�b���֔ԂŔh������Ă����k�R�Ď�ɁA���g�̎O�j�E������i���傤���傤���j�𑗂荞�B�N��͂͂����肵�Ȃ����A1490�N���̂��Ƃ炵���B���̗��R�Ƃ��ẮA�k�R�͂܂��������N�����\��������A�܂����牓���Ƃ������Ƃł���Ƃ���A�]���ƕς��Ȃ��B������i���傤���傤���j�͍��A�m���q�Ə̂���A���A�m�Ԑؑ��n���E�ɔC����ꂽ�B����ȍ~�A�k�R�Ď�͏�����i���傤���傤���j�̎q�����p���ł������ƂɂȂ�B�i���A�m������ψ��� �u�Ȃ�����3�v�j�B�@���^���̎��тƂ��āA�e�n�Ɋ������Ă����i�i�����j�������ɏZ�܂킹�A���̑���ɑ㊯������e�n�֔h�����A�n�����̗͂͂��킬�������������Ă��邪�i�������i�� �u�{���Ō�鉫��j�v�j�A���A�m�͗�O�Ƃ��ꂽ�悤���B
��͂莡�߂ɂ����n���������̂��A���邢�͏d�v�n�悾�����̂��A���̎q��h�����Ď��߂����Ă��āA�Ȃ�ƂȂ��k�R�Ď�͎������{�ɂ����銙�q�����̂悤���B
������i���傤���傤���j�̐Ղ́A�q�̉�Ђ��p�����B��ЈȌ�͏����ł͂Ȃ������Ȃ̂ŁA�܂����Ђ�����n���̖k�R�Ď��Ƃ������ƂɂȂ�B�������A���A�m�Ԑؑ��n���E�ł���B����Јȍ~�A�a���A�����A�����Ƒ����A�����̂Ƃ��ɎF���������N�U���č��A�m��͏Ă����������B�{�Ƃ̗������͏��J�i���傤�˂��j�̂Ƃ����i���A�m������ψ��� �u�Ȃ�����3�v�j�B�@
�����ƎF���Ƃ̌𗬂́A���̈ʒu�W���瑊���Â���葱���Ă������Ƃ��e�Ղɑz���ł���B��≓���ɂȂ邪�A�ȉ��^���x�����́u�V���������j�v�𒆐S�ɗ����ƎF���Ƃ̊ւ������Ă݂悤�B���^���i���傤�����j�ܔN�i1481�����{�̕����\�O�N�j�A�����͏��߂ĎF���Ɉ��D�i����Ԃˁj��h�������i�^���x���� �u�V���������j5�v �w���~���E���^���x�j�B���́u���߂āv�Ƃ����̂����������Ƃ��ď��߂ĂȂ̂��A������ɂƂ��ď��߂ĂȂ̂��A����Ƃ��u���D�v�Ƃ����F�ʑN�₩�Ȗf�ՑD�𑗂����̂͏��߂ĂƂ����Ӗ��Ȃ̂��悭������Ȃ����A����ȑO�ɂ��L�^�Ɏc���Ă��Ȃ��𗬂��������͂��ł���A�n���I�ɍl���Ă���͂��̍�����n�܂�����������Ȃ��قnjÂ��ƌ����ׂ��ł��낤�B
���^���̎O�\��N�i1508�����{�̉i���ܔN�j�ɂ́A���Ò����i���܂Â����͂�j�����f�Ղ̎�����v�����鏑�����^���ɑ����Ă���B���̌�A���^���l�\�N�i1516�����{�̉i���\�O�N�j�������@���i�͂����܁j�̎O��a��獑�G�i�݂₯�����݂̂��݂��ɂЂŁj�������v���������������邽�ߕ��D�\��ǂ𗦂��ĎF���̖V���i�ڂ��̂j�ɏI�������B�F�����E���Ò����i���܂Â��������j�͖��{�ɋ��ĘZ������V�Â̎O��G���U�ߎE�����B���̌��̂��߂��A���N�i1516�����{�̉i���\�O�N�j�\��\���A��������F���Ɏg�҂��h������Ă���B���Ò������O��G�������R�́A�����f�Ղ̌��v����邽�߂Ǝv���邪�A�Ƃɂ��������͋~��ꂽ���ƂɂȂ邾�낤�B���̌���A���^���̎l�\��N�i1518�����{�̉i���\�ܔN�j�ɓ��Ò��������^���ɏ��𑗂�����A���^���l�\�ܔN�i1521�����{�̑�i���N�j�A�����̎O�i���i���������̏d�b�Ŏ����ӔC�ҁj�����q�������ɏ��𑗂�����ƒʌ�������B���^���l�\��N�i1525�����{�̑�i�ܔN�j�ɂ͓��Ò����i���܂Â����悵�����V�����������j�����^���ɕ����A�����^���\�N�i1526�����{�̑�i�Z�N�j���^�����瓇�Ò��ǂɌ������Ă���B���̔N�A�݈ʌ\�N���}�������^���͖v�����B�Z�\��B�i�^���x���� �u�V���������j5�v �w���~���E���^���x�j
���ʂ͌ܒj�̏������i���傤���������j���p�������A���̔��N�i1534�����{�̓V���O�N�j���Â��痮���ɑ��āA�O��G�̎c�}���ēx������������ĂĂ���ƒʍ����������Ƃ����i�^���x���� �u�V���������j6�v �w�{�ÁE���d�R/�������E�������E���i���x�j�B�@���ʓI�ɂ́A�O��̍Đ��͂Ȃ������悤���B���������䂦�A�����̎O������������ɌŎ�����̂�������Ȃ����A�����䂩����Ȃ��s�������Ƃ��Ȃ��n�ɌR���𑗂邱�Ƃ͍l���ɂ����̂ŁA�����Ɠ��{�Ƃ̌��ՂƂ����̂́A�ӊO�ƍL�͈͂ōs���Ă����̂��낤�B�@����ɎO��G�́u�C�����l�v�Ƃ������i�������i�� �u�{���Ō�鉫��j�v�j�B
���������玟�j�̏������i���傤�����j�։��ʂ��p������A�������l�N�i1559�����{�̉i�\��N�j�l���A����������F���ɑ��A�������p���F�b��[�߂����Ǝg�҂𑗂�A���ËM�v�i���܂Â����Ђ��j�͂�����u�K�r�v�ł���Ƃ��鏑��𑗂�A���Ȃ�D���������B�������\��N�i1567�����{�̉i�\�\�N�j�āA�{�Ó����痮���ւ̒��v�D���F���������c�ɕY������ƁA���Î��͑D���o���ė����֑���͂����B�����́A�������\�l�N�i1569�����{�̉i�\�\��N�j���̎g�҂Ƌ��i�𑗂�A���ËM�v�����������\�ܔN�i1570�����{�̌��T���N�j�g�҂𑗂��ė��Ƌ���ɂ��f�Ղ����߂��B���̓��Î����痮���ւ̎g�҂̂Ƃ��A���V�E���������痮���̎O�i���i���������̍s�����̃g�b�v�j�ɑ��āA�ߍ������D�͈i������j��ттĂ��Ȃ��̂Œ��ׂ�悤�\�������Ă���B���łɘZ�\��N�O�̏��^���O�\��N�i1508�����{�̉i���ܔN�j�ɂ����Ò����i���܂Â����͂�j�����f�Վ�����v�����Ă���A���̎�̖��͂��̎���ɂ������Ȃ邱�Ƃ͂Ȃ��̂��낤�B�������\���N�i1572�����{�̌��T�O�N�j�ɂ͓��Î��͗����̓n�C�D�������ттĂ��Ȃ��ꍇ�̍��v�����˗����Ă���B���������������͖��f�Վ����ɔM�S�łȂ������̂��A����Ƃ��߂܂����ꂸ�ɂ����̂��A���i����N�i1574�����{�̓V����N�j���Ë`�v�i���܂Â悵�Ђ��j�̏P�����ꂷ��������̎g�ҁE�V�E����f�i�Ȃキ�j�炪����ė���ƁA�F���͔ނ�ɑ��āA�����������Ȃ��Ɛӂ߂Ă���B������ė����g�҂͉����O�\����lj����đ��낤�Ƃ������A�`�v�͂�����Ƃǂ߂āA���y�⌢�Ǖ��i���ʂ������́j�������A�����Â��ȂNJ��҂����Ƃ����B���̌���A���i���\�l�N�i1586�����{�̓V���\�l�N�j�ɂ͎F���̓�Y���V�i�Ȃ�ۂԂj�̒�q�E���@�|�i�Ƃ܂肶�傿���j��������K��A���i��������Ɏt������ȂǁA�����ƎF���̊W�͗ǍD�������i�^���x���� �u�V���������j6�v �w�{�ÁE���d�R/�������E�������E���i���x�j�B
�����ɂƂ��ĕ��������ς���Ă����͖̂L�b�G�g�̂���̂悤���B�o�_�E��q���̋��b�ŁA�V����N�i1581�j�G�g�̒����U�߂Ō��т������A����������i�����̂��傤�j�ꖜ�O��ܕS��^����ꂽ�T��䢋��i���߂�����̂�j�Ƃ��������������i�V�l�������� �u�퍑�l�����T�v�j�B�̂��Ɏq�̋T�䐭���i���߂��܂��̂�j���Ό����Øa��ˎl���O��Ɉڂ���A�����܂ő����T��Ƃ��i�����ɗY�� �u�喼�̓��{�n�}�v�j�B�@���̋T��䢋�́A�V���\�N�i1582�j�G�g�̒�����Ԃ��̍ہA�����Ɏc�����Ėї������������B�����]���������߂��A���邢�͈ȑO����䢋�ɏo�_����^��������Ă��Ȃ���ї��ƂƘa�r�������Ƃł��ꂪ�ʂ����Ȃ��Ȃ������߂��A���̂��ƏG�g��䢋��P�H��ɌĂяo���āA�]�ނƂ����u�����B䢋�͗��������]�����B�����ŏG�g�͒c���i������j�Ɂu�T�䗮����v�Ə����ԉ���������䢋�ɗ^�����Ƃ����B�Ȃ�䢋邪������]�̂��s�������A䢋�̓V�����Ƃ̌��Ղɏ]�����Ă������Ƃ�����A���A�W�A��ɏڂ��������炵���i�������i�� �u�{���Ō�鉫��j�v�j�B�@�������A�����͏G�g�̗̍��ł����ł��Ȃ��̂ŁA���̎�@�́A�M���̉H�Ē}�O���ҔC������Ɠ����Ȃ̂��낤�B�����ɂƂ��Ă͑S�����f�Șb���B
����ŁA�T��䢋�́u������v�ɑR���āA���Î������X�Ɋ������悤���i�������i�� �u�{���Ō�鉫��j�v�j�B�����͉��̃��m���A�Ƃ������Ƃ��B�������Ɨ����������ċT�䎁�Ɠ��Î��Ƃ̊ԂɃM���M���̒Ղ��荇�����������炵���B�����Ƃ��A�T��䢋邪�u������v�̒c�����������Ƃ��A���Î��͋�B�����簐i���Ă��������B�Ƃ������Ƃ́A��B�����̂̂��L�b�Ɛb�Ɂu������v�����邱�Ƃ����߂Ēm���āA�җ�ɉ^�����J�n�����A�Ƃ������Ƃ��낾�낤���B
���̒Ք��荇���̍Œ��ɓ��Î��͗����ւ̈��͂����߂Ă����B�T��䢋��i���߂�����̂�j�Ƃ̑R��G�g�ɃA�s�[�����邽�ߊ����Ă��������̂��A���邢�͋�B�����f�O�������Î������Ȃ�ڕW�Ƃ������̂��A����Ƃ������̐g���Ă�������Ƃ������Ƃ�������̂Ȃ̂��ǂ����A�ߋ��̑P�O���Ƃ͈قȂ�Ή��������Ă����B
���i���̏\�Z�N�i1588�����{�̓V���\�Z�N�j�����A���Ë`�v�i���܂Â悵�Ђ��j�͎g�҂����i���Ɍ��킵���B���̏��ɂ́A���̂悤�ɏ�����Ă����Ƃ����B
�u�����i�ق�����j�A�V���ꓝ���A�C���i���������j���Ɍ����ӁB�������i�������āj�A�����Ƃ��i�ЂƂ�j�A�E���������B�֔��A���R�ɖ����A���i�����̂��Ɓj��j���i�قӂ�j�ƁB���̎��ɋy�ыX�����g�����͂��ĎӍ߂��A�v�i�����j��A�i��j���E���C�߂A�������i���J���i�₷�炩�j���B�����ɓ��ɍ��������v
�ߑ��̍Ō�ʒ��̂悤���B���i���͂��̜������v�����ǂ����A�a�A�O������̓��N�\�ꌎ�A��\��Ŗv�����B���ʂ͈ꑰ�Ŗ����̏��J���i���傤�˂������j���p�����B����Ȓ��ł��A���Ë`�v����ւ̑Ή��ً͋}���ԂƂ���ɐi�߂�ꂽ�炵���A���N�̋㌎�A�����g�҂͓��Ë`�v�ɏ]���ċ����ڊy���i����炭�����j�ŏG�g�ɔq�y�����B�G�g�͗����J����N�i1590�����{�̓V���\���N�j��\�����t�ŏ��J���ɏ���𑗂�A�y�Y�̗���q�ׁA����ɁA
�u��A��O�N���ɓ��ɖ��i�݂�j�ׂ��B���͑����i����j�A�����ĔV�ɉ��v
�Ɩ������B�����Ƃ��Ă͑傫�ȋ������������낤�B�����œ������J����N�i1590�����{�̓V���\���N�j�����A���Ë`�v�͏��J���ɑ��āA���c���𐧂����G�g�ɏj�V�̎g�҂𑗂�悤�������킵���B���J���͗��N�̏��J���O�N�i1591�����{�̓V���\��N�j�����A�g�҂��F���Ɍ��킵�A�֔��G�g�̊֔��B������ꂵ���B���傤�ǂ��̍��A�G�g�����N�̒��N�o������O���쉮���̒z��𖽂��Ă���A���Ë`�v�͓��N�i1591�j�\�����J���ɏ���𑗂�A�֔��̒��N�ւ̏o�����߂ƁA�F���E�����ɕ����o���悤������ꂽ���ƁA�����͐l�����Ȃ��������ɓ��Ă��Ȃ��̂ŕ����o������Ɏ���l�̏\�������̕��Ƃ𑗂邱�ƁA���쉮���z��ɎQ���������ɋ���č��𑗂邱�ƁA���������B�O��W�͕�����Ȃ����A���̍��G�g�����J���ɏ��Ȃ𑗂�A���N�ւ̏����̔h���𖽂��A�����]��Ȃ��ꍇ�͂܂���������j�肷�ׂďĂ��s�����ł��낤�A�Ɯ������Ă���B�����́A���̓��{�̓����N���J���O�N�i1591�����{�̓V���\��N�j�ɓ�x�A���ɒʕĂ����i�^���x���� �u�V���������j7�v �w���J���x�j�B
���N�A���J���l�N�i1592�����{�̓V����\�N�A���\���N�j�O���A���{�̒��N�o�����n�܂����B���̔N�A��̋T�䎁�Ɠ��Î��̂��荇�����������݂��B
�G�g�́A�����ɂ����铇�Î��̗�����咣�����������Î��ɑ��ĕ��\���N�i1592�j�ꌎ�A�����𓇒Î��̗^�͂Ƃ���Ƃ������_���o�����B�����ċT��䢋�ɂ́A�ւ��n�Ƃ��āA���ꂩ�牓������\��ł��閾���̟��]�ȑ�B�i�����������傤�������イ�j��^���A�u��B��v�Ƃ����Ƃ����i�^���x���� �u�V���������j7�v �w���J���x�j�B�@�ꌎ�Ƃ������Ƃ͓�����R�n�C�̒��O�Ȃ̂ŁA���_���}�����Ƃ����Ƃ��낾�낤���B
�܂��A���̔N���\���N�i1592�j�́A�T��䢋邪����������}����̂̏G�g��������~�߂��Ƃ����i�^���x���� �u�V���������j7�v �w�N�\�x�j�B�@
���J���ܔN�i1593�����{�̕��\��N�j�A���J���͂悤�₭���D��h�����A�R���̑���̕��Ɩ����������B���Ë`�v�́A�ߔ����B���d���d�A�Ƃ��Ȃ�����A�c��̕��Ƃ�����悤�v�������B�������A���N���J���Z�N�i1594�����{�̕��\�O�N�j���J���͓��Ë`�v�ɏ���𑗂�A�c��́u�R���v�ɂ��Ă͍����������B����A�ƒf���Ă���B�Ɨ����ƂƂ��Ă̗����̈Ӓn���݂�悤���i�^���x���� �u�V���������j7�v �w���J���x�j�B
���N�o�����G�g�̎��ɂ���ďI���A���{�ł͊փ����̐킢���o�ē���ƍN�̐��ɂȂ��Ă����B�����͂��̊ԁA���J���̍����𐿂����ƂŃS�^�S�^�����������̂́A���̊Ԃ̕����ƌ����������B�������A����̗���͈�C�ɎF���̗����N�U�ւƐi��ł����B
���J���\�l�N�i1602�����{�̌c�����N�j�A�����̋A���i�v�D���Ȃ�Ɨ������̈ɒB�̂ɕY�������B�ƍN�́A�����l��S�������ɑ���͂���悤�ɒB���A����ѓ��Î��ɖ������B�ƍN�ɂ��Ă݂�A���N�o���Œf�₵�������Ƃ̍����ƌ��Ղ𗮋��ɒ���������A�����ɉ������킯���B���Î��͗����l����ň����A�����ɗ����֑������B�����ė����ɑ��āA�ӗ�g���ƍN�ɑ��邱�Ƃ�v�������B����Ƃ͕ʂɁA��ɋT��䢋邪�������U�߂悤�Ƃ����̂𓇒Î����~�߂����Ƃɂ��Ă��ӗ�g��v�����Ă����̂ŁA�����͓̎ӗ�g�v���������ƂɂȂ�B�������A�����͎F������{�ɕ�������̂��x�����A����ɉ����Ȃ������B���Ë`�v�́A�����J���\�ܔN�i1603�����{�̌c�����N�j�A���J���ɏ��𑗂�A�ӗ�g�����̉Ă��邢�͏H�Ɏ�������悤���͂��������B����ɁA�F���ł͓��Ò��P�i���܂Â����ˁ��̂��̉Ƌv�j���Ɠ𑊑����Ă���A����ɑ���j�V�̎g�������v�����Ă����B�{���̗v���ɗ����͍��f�������Ƃ��낤�B���Ò��P�ɑ���j��g�́A���N�i���J���\�ܔN��1603�����{�̌c�����N�j�㌎�A�������m�𑗂������ƂőΉ������B�������A�ƍN�ւ̎ӗ�g�E�T��j�~�ɑ���ӗ�g�E���N�o���̍ۂ̌R��s���s���S���{�ɂ��ẮA����Ȃ��ꂸ�A���Ë`�v���珮�J���֓��̏�����ꂽ�B�i�^���x���� �u�V���������j7�v �w���J���x�j�B
�܂��A�����N�i���J���\�ܔN��1603�����{�̌c�����N�j�{�Ó��̑D����j���Ĕ�O���˂ɕY�������B���Y���͑ւ��̑D��^���A�F�������đ���o�������A���̑D�͓��Î��ɉ��̘A���������A�����Ă��܂����B����Ƃ͕ʂɁA���̔N�ɂ͗����D�������i���������܁j�ɕY�������̂ŁA�F���ł͂��̑D�̏�g���ɑ��A���˂ɕY�������D�̌��ŎF���͗����Y���ɑ��Ėʖڂ��������A�Ɠ{���\���A����𗮋��֓`�������Ă���B�����ł́A���̕Y���D�̌��ł̎ӗ�̎g���𑗂��Ă��邪�A�̐S�ȉƍN�̎ӗ�g�͈���ɓ������Ƃ��Ȃ������B�u���Í��j�v�ɁA���Ò��P�i�̂��̉Ƌv�j�������̖���ɓ{��R���h�����s�����Ƃ��ċ`�v�Ɏ~�߂��Ă���b���ڂ��Ă���B�����̂��̑ԓx�́A�Ɨ����ƂƂ��Ă̌ւ肪�Ȃ����߂邱�ƂƂ��ē��R�Ǝv�����A����ȊO�ɁA�������@�卑�ł��閾�̋���ȌR���͂����|�Ƃ��Ċ��҂��Ă������Ƃ��z�肳����i�^���x���� �u�V���������j7�v �w���J���x�j�B
���J���\���N�i1605�����{�̌c���\�N�j�A�������B���痮���A���r���̗����̐ڍv�D�i������������j���啗�ɑ����A�܂������˂ɕY�������B����ɑ����{�́A�ݕ��̖v���A�Y���D�𗮋��֑���Ԃ��̂ɓ��Î��͊ւ��Ȃ����ƁA�ɒB�˕Y���D���ٗ�����n�����邱�Ƃ����Y���ɖ������B���Î��ɔC���Ă����̂ł͉����܂Ōo���Ă��ӗ�g�͖����A�Ƃ����������Ƃ̍��𐳏퉻�Ɩf�Ղ͖����A�Ƃ������f���낤�B���Î��ɂƂ��Ă͑S���ʖڂ������Ă��܂����i�^���x���� �u�V���������j7�v �w���J���x�j�B�@����ɁA���Ò��P�i�Ƌv�j�͂��̂Ƃ��������������ӂ����Ƃ����i�������i�� �u�{���Ō�鉫��j�v�j�B�@���̌�ǂ������o�܂����������悭������Ȃ����A�Y���D�͎F�����o�R���ė����A���ꂽ�B�Y���D�̏�g���E�����t�i���イ���債���ߔe�e�_��G�����Ȃׁ͂[���傤���イ�j�͎F������A���������̐擱���J��Ԃ����߂�ꂽ���A�Ŏ������Ƃ����i�^���x���� �u�V���������j7�v �w���J���x�j�B
�����J���\���N�i1606�����{�̌c���\��N�j�A���Ò��P�͍]�˂֏�菫�R�G���ɔq�y�A���̌㕚���ɂđ�䏊�ƍN�ɔq�y���A����恂������āu�Ƌv�v�ƂȂ�B���̂Ƃ��A���ÉƋv�͉ƍN�ɑ��āA�����̔���i���A�u�哇�����v�𐿂��A�����i�^���x���� �u�V���������j7�v �w���J���x�j�B�@
���������ł͂Ȃ��A�Ȃ��������哇���B���Î��ɂƂ��ẮA�܂��哇���U�ߎ�肻�̌�ɗ������U�߂���肾�����̂��A�哇���U�߂���ٗ���ŗ������܂�Ă���Ɣ��f�����̂��A�����ォ�����̗v���ő哇�o�����Ó��������̂��A���邢�͉ƍN�������̂��Ƃ𖾂Ƃ̌��E�f�Ղ̒�����Ƃ��Ċ��҂��Ă���̂𓇒Î��Ƃ��Ă͒m���Ă���̂ŁA�u�哇����v�������o���ĉƍN�̕���T����肾�����̂��A������Ȃ��B
�哇�́A�O�R��������ȑO�A�p�c���i�����������j�̂Ƃ��ɗ����i���R�j�ɓ��v�����Ƃ����i�^���x���� �u�V���������j1�v �w�p�c�x�j���A����͓`���̔��e���Ǝv���B�����Ǝ��オ�����āA��ꏮ���Ō�̉��E�������i���傤�Ƃ������j�͊�E���i���������܁j�����Ă����i�^���x���� �u�V���������j4�v �w�������x�j�A�Ƃ������Ƃ́A���̍��ɂ͉����哇�͗����̑��̂ƂȂ��Ă��āA�p�c���͂�����f�ʂ肵�Ċ�E�����U�߂邱�Ƃ��ł����ƍl������B����ł��A�����ƈ��ׂ��������̂ł͂Ȃ��A�������i���傤����������������̊�b����������^���̎q�j�̂Ƃ��ɂ͖d�����N�������哇���x�ɂ킽���ē��������Ƃ����i�^���x���� �u�V���������j6�v �w�������E�������E���i���x�j�B
�ƍN�̋������t�����F���͑哇�����̏�����i�߂����Ƃ��낤�B�������A���̌v��͗��N�ɉ��������B���̔N�A���J���\���N�i1606�����{�̌c���\��N�j�A���̏��J���ւ̍����g�������֗������߂��B���J���ɂƂ��Ă͑��ʏ\���N�ڂɂ��Ă悤�₭�̍����ł������킯�����A���얋�{�ɂƂ��Ă͍����g��ʂ��Ė��Ƃ̌��̎��������߂邩������Ȃ��Ƃ̊��҂����������Ƃ����������B���Ë`�v�͏��J���ɑ������f�Ղ̒�����s���悤�������鏑���A����ɓ��ÉƋv�́u�喾�V�g�v�i�����g�j���̕������A�����A��g�҂ɑ����Ă���B�������A���ʂƂ��ē������ɐi�W�͂Ȃ������i�^���x���� �u�V���������j7�v �w���J���x�j�B
�u�哇����v���u�����v�ƂȂ����Ƃ����͕̂\���̏�ł̂��Ƃł����āA������͔����ɖ߂����̂��낤�B����̉�Ђ̒��ł����X���邱�Ƃ��B
�����J���\��N�i1607�����{�̌c���\��N�j���哇����͍s���Ȃ������B�����g�ɏo��������̕����̕ԓ���҂��Ă����̂�������Ȃ��B�������A���̓������Ȃ��܂܂ł������̂ŁA���̗��N���J����\�N�i1608�����{�̌c���\�O�N�j�A�ƍN�͓��Î��ɗ��ٖ��̌��𖽂����B�����ƎF���̊ԂŎg�҂��s�����������A���ɐi�W�͂Ȃ������B�Ƃ��Ƃ��Ƃ��ς₵���̂��낤�A���Ë`�O�͏x�{�֎g�҂�h�����A�ƍN�ɑ������N�U��\������A�ƍN�͗��������i�^���x���� �u�V���������j7�v �w���J���x�j�B
�哇�N�U���痮���N�U�ɕ��j���ς���Ă��邪�A�ǂ̂悤�Ȏv�f���������̂��A�悭������Ȃ��B����ɚ��̂����Ȃ����������ɑ��A��C�Ɍ��������邽�߁A�Ƃ������Ƃ��낾�낤���B
�ƍN�̏��F�������N�U�ł��������A���{�͉��Ƃ��~�߂悤�Ƃ��铮����������B���N�����A�ƍN�͎F���ɑ��A�R���x�͎璼�F�i��܂������邪�̂��݂Ȃ��Ƃ��j��ʂ��ė����o���̏������w�����A�����ɍ���x�̌��𖽂����B�㌎�ܓ��ɂ����l�̏�����o���Ă��邪�A����̎F���͗����N�U������i�߁A�㌎�Z���u�����n�C�V�R�O��@�x�V���X�v�����B���{�͏\�ꌎ��\�O���{�������i�ق܂����݁j�����ÉƋv�ɁA�����N�U�͖��p�A�Ə��𑗂�A�\�R�����F�͍���x�ƍN�̏�ӂ�悤�ɁA�Ƃ̏����Ƌv�ɑ����Ă����i�^���x���� �u�V���������j7�v �w���J���x�j�B
�����A�{����R���̏���ɓ��Î����ǂ��Ή������̂��A�s�����B
�����ė��N�A�����N�U���s��ꂽ�B�ȏ�̌o�܂��番����悤�ɁA�F���̗����N�U�́A�悭������ΊO���Ճ��[�g�Ɛ�̂悤�ȒP���ȓ��@�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��B
���J���̓�\��N�i1609�����{�̌c���\�l�N�j�Z���A���R�����q��v���i����܂�������Ђ������j�叫�A���c���Y���q�呝�@�i�Ђ炽���낤��������܂��ނˁj���Ƃ���F�����O��͎��������o�q�A�R��ŕ��҂��̂̂��A�O���l���R����o�q�����i�^���x���� �u�V���������j7�v �w���J���x�j�B
�F�����j���u�����n�C���X�L�v�ɂ��ƁA�O���l���̖�A���V�i�Ǖ����ɓ����A�O�������哇�̐[�]���Y�ɒ����A�������������s���Ă����i���A�m������ψ��� �u�Ȃ�����3�v�j�B�@���̐[�]���Y�Ƃ����̂͊}���p�i�̂ǂ����j�̂��ƂŁA�����ɗ��������̏o��@�ւł���u�����i������Ɓj�v�������āA����𓇒ÌR���U�������Ƃ����i�^���x���� �u�V���������j7�v �w���J���x�j�B
�O���\����[�]���Y���o�`�A�\�������\�ܓ��܂ő�a�l�i�哇�̒������j�ɐ����A�\�Z���o�`�����̌Ì��i�哇�̐��[�̐��Ì��j�ɓ����A���҂���J�̂��߂ɐ������āA�O����\���o�`�A�H���i�哇�ׂ̗̉��v�C�����̓암�j�A�O����\������V���̋T�Ái���V��������t�߁j�ɓ������āA����\����R�������Ă����i���A�m������ψ��� �u�Ȃ�����3�v�j�B�@���V���ł́A�����̓��������u�������i�Ђ炶��j�v������A���̎���������ÌR���}�������Ă���B���ÌR�͓S�C�𗁂т��Ȃ���i�R���A������͎R���֓������B�����œ��ÌR�͎O����\����R�������A��������ł���u�ԏO����i�イ�ʂ��ǂ�j�v�^�ߌ��e�_�㒩�q�i��Ȃ�ׁ[���傤���j��߂����B���q�͈����o���ꏈ�Y����悤�Ƃ����Ƃ��A�F���R�̒��ɒm�荇���̐w�m�����āA���̂������ŏ�����A�ߗ��Ƃ��ė����֘A��čs���ꂽ�B���̒��q�̎l��̑����A�����̍����u�g�x�i���݂��ǂ�j�v��n�n����ʏ钩�O�i���܂��������傤����j���������i�^���x���� �u�V���������j7�v �w���J���x�j�B
���̌�̓��ÌR�́A�O����\�l���ɉ��i�Ǖ����A�O����\�ܓ��Ɂu���ق�v�ɒ������B���A�m�̓��A�ÉF�����̂��Ƃ����A�����ł͂��������͈͂��L���ĉ^�V�`�ƍl�����ق����ǂ��������B�u�S�̉^�V�v���u�D���v�|�|���Ȃ킿�����n���邢�͕�`�Ƃ����Ӗ����낤�|�|�Ƃ����ƋL����Ă��邩�炾�i���A�m������ψ��� �u�Ȃ�����3�v�j�B�@���悢��F���̌R��������{���ɏ㗤�����킯�����A���̂Ƃ��̎�����̗l�q���u������L�v�ł́A�u���A�m�ɕ��D���ƕ��ւ����A�����̑����s�B�ƍ�����𓌐���k�։^�o����l�A�O�㖢���̎����Ȃ�v�Ɠ`���Ă����i�^���x���� �u�V���������j7�v �w���J���x�j�B
�����ɐN�U���Ă���F���R�ւ̑Ή��Ƃ��ė����ł́A�F���R���哇�ɓ������Ƃ̕O���\���ɓ���A�V�������V�Ɩk�J�e�_���i���Ⴝ��ׁ[����j���g�҂Ƃ��ċ}�h���Ă���B�F�����̋L�^�u�����n�C���X�L�v�ɎO����\�O�����V�����𗮋��D���哇�����ċ삯�čs�����A�Ƃ����āA���łɓ��V���ł̐퓬�ƎR�����I���Ă��鍠�A�����̎g�҂͑哇�������Ă������Ƃ�������B���̌�A���Ð������A�m�ɓ�������ƁA��x�ڂ̎g�҂Ƃ��Đ����@�e�B�i�����炢��������j���V�E����ǖL�E�]�F�h�^����O����\�Z���A�h�������i�^���x���� �u�V���������j7�v �w���J���x�j�B
���Ð��͎O����\�Z���͋x���A�O����\�����ɍ��A�m����Ă������ɂ����i���A�m������ψ��� �u�Ȃ�����3�v�j�B�@����A���������̎g�҂́A���H�͓G�����[�����Ă���ƕ����A�r���̑q�g�i����́����[���v�Ǘt�j�Ŗ閾����҂��D�ɏ���āA�O����\�������A�m�ɓ��������B���̂Ƃ��A�F���R�́u�叫�R�͍��A�m��߁v�ɏo�Ă��ĉ�Ȃ������B�܂荡�A�m����U�ߗ��ĂĂ����̂��B�����g�ҁE�e�B��́A���Õ��̑厜�����_��ƑΖʁA�a�r�̌��ɗՂ��A���Õ��͘a�r�̘b�͓ߔe�ōs���A�Ǝ�荇��Ȃ������̂ŁA�g�҂͂��̓��[���A�����i�^���x���� �u�V���������j7�v �w���J���x�j�B
���A�m��ł̐킢�͏ڂ������Ƃ͕�����Ȃ��B�u�Ȃ������R�v�ł́A�퍑����̐푈�̂悤�Ȑ퓬�������l�q�݂͂��Ȃ��A�Ƃ���A�u�V���������j�V�v�ɂ́A�k�R�Ď�E���A�m�i���e�i���傤�悤�j���O�X�N�Œ�R�����̂ŕ��c���Y���q�呝�@�����������A�Ƃ���B
�퓬���Ȃ������Ƃ��鍪���́A�u�����n�C���X�L�v�́u��������̏邠���̂���v�ƁA���A�m��͖��l���������Ƃ��炫�Ă���悤���i���A�m������ψ��� �u�Ȃ�����3�v�j�B�@�������A�����ɂ͂���ɑ����āA�u��������̏邠���̂���B���m�����ɁA�₩�ɑł܂͂�Č�āA���X������B�v�Ƃ���̂ŁA���l�ƌ��������A�m�邾�������A�}�Ɏˌ��i�|��H�j�����̂ł��������ɕ����Đ퓬�ɋy�A�Ɠǂނ̂����R�ł͂Ȃ����낤���B���̂Ƃ��̖k�R�Ď�͌ܐ��̌������ł��邪�A�����Ƃ����̂�恂ł���A����肪���e�i���傤�悤�j���i���A�m������ψ��� �u�Ȃ�����3�v�j�B�@�����āA���A�m�i�E�����͍��A�m��Ă������̗����A�O����\�����Ɏ��S���Ă���B�^�V�̑�k�i���[�ɂ��j��ɂ͗��̖k�R�Ď炪�����Ă��āA�̉�E�l�������E�L���̂Ȃ��l���E�Z����c�E�����]����̖����L����Ă���Ƃ����B�����ŁA�L���̂Ȃ��l�����A�ܐ��̍������ƍl�����Ă����i���A�m������ψ��� �u�Ȃ�����3�v�j�B�@���Î��ɒ��ڐn���������l���Ȃ̂Ŗ������A�ƍl����A��͂荡�A�m��ł͎F�����Ă������ɂ���قǂ̌������퓬���������ƍl���ėǂ��������B
���A�m��𗎂Ƃ����F���R�́A�O����\����^�V�`���ǒJ�̑�p�i�������j�ɓ����A�������畺���ɕ������H�ƊC�H�œ쉺�����B�l������C�H�̎F���R�͓ߔe�`�ɐN�U�A�O�i���̂ЂƂ�Ӗ��e�����R�i����Ȃ��₩���肴��j�A�h�E�i�Ă��ǂ��E�E�h�E�͂���ɂ傤�ɓ��j���L����e�������i�Ƃ݂��������₩�����������ьp�c�����������j�ƂƂ��ɓߔe�`�̎���ɂ������Ă����B�`���ɂ͉��Ǎ��X�i��炴�ނ��j�Ƃ����ŐV���̖C��ƁA���̑Ί݂̎O�d���i�݂��������j�Ƃ����v�ǂ��\���A�܂��`���̊C���ɂ͓S�������菄�炳��Ă����Ƃ����A�߂Â��Ă����F���R����U�͌��ނ������Ƃ����B����A���H�͊��R�v�������畺�𗦂��Ė��Ƃɕ����Ȃ���i�R�A�Y�Y��Ɨ��������Ă������Ď�ڎw�����B�����R�͉z���e���i���������₩���j������S�����C���̖k�A�啽���i�����Ђ���j�ŎF���R���}�����������A�Γ�e���g���F���R�ɋ��A��ԍ��q�e�_�㐷���i�������܂����ׁ[���������j������������펀�A�������͑�����ƂȂ����B�F���R�͎鉺�̖��Ƃ��Ă��������i�������i�� �u�{���Ō�鉫��j�v�j�B
�����̏��J���͍~���A���͎F���R�ɐڎ����ꂽ�B���̂Ƃ��O�i���̂ЂƂ�Y�Y�e���i���炻�����₩���j�̎O�l�̑��q����̕��𗦂�������E�o�����B�F�����͖@����E�q���i�ق�����ɂ�����j�Ɛ����V�i��������ڂ��j�������ǂ��A�������i�����Ȃ�j�Œǂ����č���ƂȂ����B�O�Z��͓������ꂽ���A�F�������@���������A�����V�͓��������B������u�������̐킢�v�Ƃ����i�^���x���� �u�V���������j7�v �w���J���x�j�B
�������ė������́A���i���j�̍������Ȃ���A����ŎF���̑����Ƃ����ɗ������鍑�ƂȂ����B���J���͎F���ɘA�s����A���N���J����\��N�i1610�����{�̌c���\�ܔN�j�����\�Z���A�x�{�ʼnƍN�ɔq�y�A������\�����]�˂ŏ��R�G���ɔq�y�����B�ƍN���G�����A���J����b���ł͂Ȃ��O���̗��o�Ƃ��Č������ĂȂ����Ƃ����B���J���͖����ېV�ȑO�ŗB��]�˂ɏ�����������ƂȂ����B���J���������ɋA������̂͗��N���J����\�O�N�i1611�����{�̌c���\�Z�N�j�\����\���ł���B�A�����O�A���J���ւ̒m�s�ژ^�ɂ�艂�������͎F���̒����n�Ƃ���A�܂��Ӗ��e���A�h�E�i����Ȃ��₩���Ă��ǂ��j�͏��Y���ꂽ�i�^���x���� �u�V���������j7�v �w���J���x�j�B
�F���ɏĂ��������ꂽ���A�m��́A���̌㕜������邱�Ƃ͂Ȃ������B�Ă������̂̂���̎��ӂɂ��������A�m���Ǝu�c�^�����u�ꏊ���ǂ��Ȃ��v�Ƃ������R�ŊC�݂̋߂��ֈړ�����ƁA���A�m�i�i�k�R�Ď�j�Z���̓�c�͕s�ւ��Ƃ������ƂŊC�߂��̍��A�m���i�H�j�ɏZ�ނ悤�ɂȂ����B�Ď琧�x���`�[�����Ă������Ƃ��v���Ƃ����B���A�m��͋���Ƃ��Ă̋@�\���������̂��B���̎����]���̂Ƃ����A�m�i�͎ֈڂ�Z�B����ȍ~�A�����ېV�Ɏ���܂ō��A�m�i�͑�X�ꑰ���p���ł������A���A�m��͑ł��̂Ă��Ă����悤���B��\����敂̂Ƃ��A���A�m��̓y�n���S���Ɏ������肪�N�������A��敂́u���A�m����}�v���쐬���A��n���q���ւ̉i���n�ɂ��邱�Ƃ��肢�o���B�ǂ���狖�����炵���A��n���Ɂu�R�k���A�m��Ď痈���L�v�𗧂Ă��B����͌��݂ł��c���Ă����i���A�m������ψ��� �u�Ȃ�����3�v�j�B
�Ō�ɁA���ג��㗤�`���ɐG��Ă��������B���ג��i�݂Ȃ��Ƃ̂��߂Ƃ��j�Ƃ����̂́A�������������Y���ג��i�����͂��낤�݂Ȃ��Ƃ̂��߂Ƃ��j�̂��Ƃ��B���̈ג��������֗������Ƃ�����A�Ƃ����B
�����ɂ���Ă����o�܂͏�������悤���B��́A�ג�����B�֗������\�ꂵ�Ă�������ɗ����ɓn�����Ƃ�����́A�ʂ̈�͕ی��̗��̂̂��ג����ɓ��哇�֗�����A�܂���\�ꂵ�Ă�������Ƃ�����́A����Ɉɓ��哇���甪�䓇�܂Ő������Ĕ��䓇����D�o�����Ƃ��ɗ����ɓn�����Ƃ�����́A������悤���B������̏ꍇ���A�C��Ŗ\���J�ɑ����A�^��V�ɔC���ė��ꒅ�����̂��A�����̉^�V�i����Ă�j�A���Ȃ킿���A�m�̊O�`�Ƃ������ׂ��^�V�`�ł���A�ƂȂ��Ă���B�₪�Ēn���̑嗢�i�i�������Ƃ����j�̖��Ɨ����ɂȂ�q�����܂ꂽ���A�ג��͕�q���c���ē��{�A�����A���̂Ƃ��̎q���̂��̏w�V�i�����Ă�j�ł���A�Ƃ����̂��`���̂��炷���ł���B�w�V�́A�_�b�̓V�����������āA���߂ė����̉��ƂȂ����Ƃ���Ă���l�����i�^���x���� �u�V���������j1�v �w�w�V�x�j�B�@���̓`�������n�ɂ��č]�ˎ���ɑ��n�Ղ��������̂��u���|�����v�ł��邪�A�����������ɂ��ƁA���̓`���͌���ł�����̎q�������ɂ͐g�߂Ȃ��̂ł����āA�{���̘b���ƐM���Ă���q���������̂��������i���������� �w�O���猩�������x�@�u�V�F���w�V���[�Y�R�F���E�����E�����v�j�B
�܂��A�`���Ȃ̂ŁA���̎j���̗L����₤�͖̂��Ƃ������̂����A�����O�\�N�ォ��吳�ɂ����Ďj�����ǂ����̘_��������A���ł́A�����̂Ȃ����b�ł���A�Ƃ����̂�����ɂȂ��Ă���炵���B���b���u������v���@�Ƃ��ẮA1650�N�Ɂu���R���Ӂv�������ی����H�n���G���A�F���Ƃ��a瀂�����A�u���Â��������������������̏o�ł���v�Ɩ��O�����߁A�Ƃ����̂�����ɂ�������߂̂悤���i�V�l�������� ���{��s�̌n1 �w���A�m�O�X�N�x�j�B�@�����A���̉��߂ɂ��ẮA���łɖ�������ɓ����[���Վ����w�E���Ă���悤�ɁA�F���̗���������ȑO�A�ܒ���l���ג��̗����㗤�̘b���L���Ă������i�V�l�������� ���{��s�̌n1 �w���A�m�O�X�N�x�j�A��������Ɍ��m���̌��D���V�̕��W�ɂ��L����Ă��āA�F���ɋC�������悤�ɂȂ�ȑO���痮���ł͂��łɓ`���ƂȂ��Ă����Ƃ����i�^���x���� �u�V���������j1�v �w�w�V�x�j�B�@�����ł́A����ȏ㗧������Ȃ����Ƃɂ��āA���łɗ^���x�����͗����ɏ㗤�����l�����ג��ł͂Ȃ��������l�Y���i�i�����ւ����낤���������j�Ɛ��肵�Ă���V�����Љ��ɗ��߂悤�B
�����A�m��ւf�n�I�i�o��L�j
�����Q�O�N�i2008�j�U���V���i�y�j
�����͐��E��Y�E���A�m��ɂ���Ă����B�c�O�Ȃ���V��͉J�͗l���B
��̓����A�u���ꌔ�v��鎖�����͖��l�Ńl�R���炯�A�`�P�b�g�͎����Ŕ��ɓ���Ă��������A�ƂȂ��Ă������A�Ȃ�Ƃ��m���r���������̂��B

�܂��͐���A�u���Y��v���B

�䕗�̑����n���̂��߂��A�h�b�V���Ƃ����d��������̖傾�B��̗����ɓ���A�����J���Ă���B��Ԃ��H�Ǝv�������A��̌��݂��炢���Ă���Ȃ͂��͂Ȃ��B

�Ǝv���ė��ɉ��ƁA���Ɛ̏������ɂȂ��Ă��āA��������̂������̂悤�ɊJ���Ă��錊�������B��Ԃ̕������B�Ƃ������Ƃ́A��ԂƂ��Ă��@�\�����̂��낤�B

�傩��܂������Ώ�̓����L�тĂ��邪�A���̓����̂͐��ɍ��ꂽ�̂��������B
���̓˂�������Ɂu����i���[�݂�[�j�v�ƌĂ���Ԃ�����B���z�[���y�[�W�ł͕X�I�ɋȗցi�s�j�ƌĂԂ��Ƃɂ��āA�u����i���[�݂�[�j�v�s���B
�����͍��J�̍s����ȗւ��������B���\�L�����B

�������獶�i�k�j�֍s���ƁA�u������i���[����j�v�s���B�����ɂ͏��������������������ŁA����Α剜�݂����Ȃ��̂��B

������i���[����j����̒��߂͑f���炵���B����Ă���A�������Y�킾�������낤�B�ቺ�ɂ́A�u����i���[���݁j�v�s���L�����Ă���B���Ă̕����P���ꂾ�������B

������i���[����j���瓌�ɂ����ƁA���A�m��́u��s�v���B��������͌����̑b�����@���ꂽ�Ƃ������ƂŁA���n�ē��ɂ��Ɩk�R�Ď玞��̌����̐Ղ��������B

�b�̊ԂɊۂ��Αg������B�����̒��Ɉ�˂��������̂��H�ƕs�v�c�Ɏv���āA��ňē����Ŏ��₵���Ƃ���A��˂ł͂Ȃ��F�̐Ղł́H�Ƃ̂��Ƃ������B
��s���牺���̂����ƁA�u�u�c�^���i�����܂��傤�j�v�s��������B���̍��፷���悶�o��̂͑�ς��낤�B

���̎u�c�^���i�����܂��傤�j�s�։���Ă݂�B���Ȃ�L�����A�s���̂��傫���X���Ă���B���̒��R�ɍ���Č��������Ă��̂��낤�A����������Y�������Ă���B

�s�̓�[�ɂ͐Ί_������Ă��邪�A�������A�u�c�^���i�����܂��傤�j�̐Ղ��������B��̍\������A���ߎ��ɂ������傾�B�Ƃ������Ƃ́A���b�u���Ђ����Ɏ艺�𑗂荞�̂́A�����Ȃ̂��낤���B

����ɂ��Ă��A�悭���ꂾ���̐�����ȎR�A�J�A�Ζʂ̒��ɐςݏグ�����̂��B�Ɗ��S���Ȃ��獡�A�m�����ɂ����B
�����A�m����
��1416�N�i���̉i�y14�N�j�A���邢��1422�N�i�i�y20�N�j�A���b�u�͍��A�m��ɖk�R���E�����m�i�͂j���U�߂��B���A�m��͌���ŎO���Ԃ̍U���Ƀr�N�Ƃ����Ȃ������̂ŁA���b�u�͌v����p���A�����m�̏��E�{�������𗣔������ė��邳�����B�k�R�����͖łт��B�i�^���x����
�u�V���������j2�v�j
�����J��21�N�i1609�����{�̌c���\�l�N�j�O���A�F���̗����������s���A�O����\�������A�m����Ă������ɂ����B�k�R�Ď�́E�����͗���̗������S�����B�i���A�m������ψ���
�u�Ȃ�����3�v�j
�ȏ�
���̃y�[�W�̐擪�ɖ߂�
![]()
�g�b�v�y�[�W�@�@�����̏��@�@�����ȊO�̏��@�@��ȊO�@�@��̈ꗗ